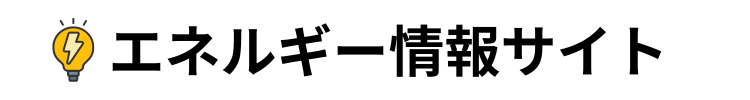2025年2月に第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました。
第7次エネルギー基本計画において再エネがどのように位置づけられているか確認してみます。
第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました(経産省 2025年2月18日)
第7次エネルギー基本計画では、2040年度の電源構成において再エネは40~50%程度を賄うとされており、主力電源化が明記されています。
以下に、第7次エネルギー基本計画における再エネの位置付けをまとめてみました。
①総論
- 周辺地域の住民への説明会の開催等、関係法令の違反事業者への交付金一時停止、再エネ特措法の認定手続き厳格化など規律強化を図る
- 地域共生型の再生可能エネルギーの導入を推進するため、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図る地方公共団体の条例の策定等を促進し、少なくとも100箇所の地域で、地方創生に資する脱炭素化の先行的な取組を2030年度までに実現する
- 太陽光パネルについては義務的リサイクル制度を含めた新制度の構築に向けて検討を進める
- FIT・FIP制度を前提としないビジネスモデルによる再生可能エネルギー発電事業を推進
- FIP制度を活用することで出力制御量を抑制し、電力市場への統合を進める
- 太陽光パネルの生産等の関連産業は外依存度が高いため、国内に強靱なサプライチェーンを構築し、産業競争力の強化を図る
昨今、太陽光発電や風力発電をめぐる地域でのトラブルが頻発しており、それらを意識した内容が入っているようです。地方自治体を中心に公的部門で積極的な推進を図るのは当然のことでしょう。国民負担の抑制も意識されており、FITやFIPに依存しない自立した再生可能エネルギーを目指しているようですが、どこまで実現できるかは疑問符です。
FITおよびFIPについては以下にまとめています。
②太陽光発電
- 次世代型太陽電池(軽量・柔軟等の特徴を兼ね備えるペロブスカイト太陽電池)について、国内に強靱なサプライチェーンを構築し、産業競争力の強化を図る
- 屋根設置太陽光発電について、公共部門は、2030年に設置可能な建築物等の約50%、2040年に設置可能な建築物等の100%に太陽光発電設備を設置することを目指す
- 住宅用太陽光発電については、2050年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されることを目指し、2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す
- 地上設置太陽光発電については、優良農地の確保を前提に、営農が見込まれない荒廃農地への再生可能エネルギーの導入拡大を進める
太陽光発電パネルは中国製が席巻しており、エネルギー自給率の観点からも国産太陽光パネルの普及は喫緊の課題と言えます。住宅用太陽光発電の普及も進めていくとのことですが、設置費用はそれぞれの家庭が負担することから、状況によっては様々な補助制度が必要になるように思います。メガソーラー(地上設定太陽光)の設置場所は限られてきていることから、荒廃農地をターゲットとしているようですが、昨今の生鮮食品の高騰・食料自給率の向上などを考えれば、本当に農地を太陽光発電に利用するのが良いのかどうかはまだまだ議論が必要です。
③風力発電
- 洋上風力発電は我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」
- 陸上風力発電は、事業実施への地域の懸念を背景に、運転開始に至っていない事業が存在しているが、こうした地域の懸念に適切に対応した上で、導入を推進
現状、国内において風力発電はほとんど普及していません(2023年において総発電量の1%程度)。洋上風力発電が「切り札」とされていますが、昨今、洋上風力発電も採算性が厳しいとされており、前途多難のように感じられます。
④地熱発電
- 中長期的には競争力ある自立化した電源としていく
- 現状の4倍以上に地熱資源のポテンシャルを拡大する可能性がある次世代型地熱技術の開発も進める
- 次世代型地熱技術(熱水のない場所でも発電が可能なクローズドループ、地熱増産システム、地下深くの高温・高圧な熱水を活用した超臨界地熱)について、2030年代の早期の実用化を目指し、研究開発・実証を進め、事業化につなげる
地熱発電も普及しておらず(2023年において総発電量の0.35%程度)、今後の技術革新に期待です。
⑤水力発電
- 安定した出力を長期的に維持することが可能な脱炭素電源として重要
- 堆砂の深刻化等による設備容量の減少、激甚化する豪雨災害等による被害、経年に伴う設備の老朽化も見られる
水力発電はこれまでも安定した再エネであり、今後も重要な電源となるでしょう。ただ、災害による被害や老朽化などにより水力発電の能力が落ちており、今後どのようにメンテナンスすべきかが大きな課題と言えるでしょう。
⑥バイオマス発電
- 発電コストの大半を収集・運搬等の燃料費が占める構造にあることに加え、昨今では燃料需給のひっ迫も見られ、事業の安定継続が課題
- 国産木質バイオマス燃料の供給拡大に向け、関係省庁が連携し、林地残材等の更なる利用に向けた体制構築、各地域に適した早生樹や広葉樹等の育林手法等の実証、適正な再造林等を推進する
- FIT・FIP制度による支援の在り方や、調達期間及び交付期間が終了した後のバイオマス発電事業の継続の確保について検討
バイオマス発電はごみ発電(ごみ焼却時に発電)を除けば、燃料の収集コストが割高となり、ビジネスとしてどこまで成立するかは大きな疑問です。おそらく、FIT・FIP制度が終了すると共に、大半のバイオマス発電は閉鎖されるのではないかと予想しています。残るのは燃料収集コストのかからない(ごみは発電の有無にかかわらず収集・焼却されるため)ごみ発電だけになるのではないでしょうか。
再エネは今後も重要な電源ですので、引き続き、国の方針も確認していきたいと思います。