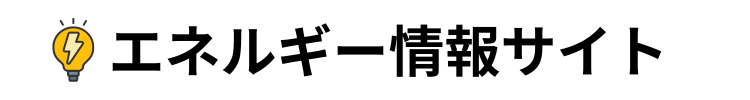2024年12月に第7次エネルギー基本計画の案が示されました。
第6次エネルギー基本計画と第7次エネルギー基本計画を見比べながら、原子力政策について内容がどのように修正・更新されたか確認してみます。
第6次エネルギー基本計画が閣議決定されました(経産省 2021年10月22日)
第7次エネルギー基本計画(案)に対するパブリックコメント(意見募集)(経産省 2024年12月27日)
第7次エネルギー基本計画では、2040年度の電源構成において原子力は20%程度を賄うとしており、今後も重要な電源として位置付けられています。
エネルギー基本計画で示された電源構成の変遷(エネルギー情報サイト 2025年1月3日)
まず、技術開発や安全性向上において、ATENA(原子力エネルギー協議会)が言及されています。ATENAとは原子力メーカーと電気事業者の連携組織であり、いわゆる原子力を推進・利用する側の組織です。また、海外機関の連携も明記されています。国内だけの研究開発では限界があるため、海外との連携や必須と言えるでしょう。
メーカー等も含めた事業者間の連携組織であるATENA(原子力エネルギー協議
会)が、学術界、海外機関等と連携しつつ、共通技術課題について、ガイドライン策
定等を通じて取組方針を示し、各事業者のコミットを得て実行状況を継続的に確認し
ていく。
核燃料サイクル推進の基本方針に変更はありません。
【第7次エネルギー基本計画】
我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点
から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイ
クルの推進を基本的方針としている。
核燃料サイクルについて、六ヶ所再処理工場の竣工遅延などが続いてきた現状を真
摯に受け止め、直面する課題を一つ一つ解決することが重要である。
六ケ所再処理工場とMOX燃料工場の竣工については、「必ず成し遂げるべき」という強い言葉で記載されており、第6次基本計画の時よりもさらに非常に強い意志が感じられます。
【第7次エネルギー基本計画】
核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場の竣工は、必ず成
し遂げるべき重要課題であり、同工場の竣工に向け、審査対応の進捗管理や必要な人
材確保などについて、官民一体で責任を持って取り組む
【第6次エネルギー基本計画】
核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場が2020年に
原子力規制委員会から規制基準に基づく許可を得たところであり、安全確保を大前提に、
関係事業者による支援も含め、これらの施設の竣工と操業に向けた準備を官民一体で進める。
2030年度までに、少なくとも12基の原子力発電所でプルサーマルの実施を目指すという計画も維持されています。
高レベル放射性廃棄物の国が前面に立ち解決するという方針には変更ありません。地層処分は科学的知見に基づき妥当であることが明記されるようになっています。ここにも国の強い意志が感じられます。
【第7次エネルギー基本計画】
我が国において地層処分が技術的に実現可能であることを改めて確認してきたところである。
最終処分の実現に向け、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針に基づき、
国が前面に立ち取り組む。
また、第7次エネルギー基本計画からは「既存炉の最大限活用」と「次世代革新炉の開発・設置」が明記されています。
「既存炉の最大限活用」では、原発が再稼働したことにより九州・関西エリアにて電気代が3割安くなったことに言及し、原子力発電が国民生活や経済活動において重要であり、その活用を進めていくと明記されています。原発は新規建設すると建設費が高騰していることから必ずしも電気代が安くなるとは限りませんが、既存炉を再稼働させる分には、すでに建設済みであることから確実に電気代は安くなります。
また、高経年化の対策や設備利用率の向上についても言及されています。高経年化は既存炉をできる限り長く利用することを想定しているものと考えられます。電気代のことを考えれば既存炉を長く利用するのが合理的ですが、安全性を考えれば早めに新型炉へリプレースした方がより合理的かもしれません。ここは悩ましい所です。
「次世代革新炉の開発・設置」では、”廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを対象”と明記しており、廃炉にした原発の跡地が次世代革新炉の建設地として想定されているようです。これから新たに原発を誘致する地方自治体が現れる可能性が皆無であることを考えれば、すでに原発があった場所に新型炉を建てるのが最も合理的な考え方だと言えます。
第7次エネルギー基本計画は原発推進へ非常に大きく舵を切っていることが伺えます。