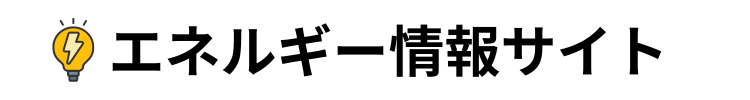代表的な化石燃料の石炭・石油・天然ガスの基礎知識をまとめました。
石炭
大昔(数千万年前~数億年前)に植物が湖や沼の底に積み重なり、地中の熱や圧力の影響による高温・高圧化条件下で炭素が濃集したもの。
無煙炭:練炭・豆炭(まめたん)・コークスの製造に用いられる。豆炭とは豆状に成形した固形燃料です。コークスとは石炭を高温で蒸し焼き(乾留)して作られる燃料で、製鉄や非鉄金属の精錬、ガラスの原料になります。
原料炭:製鉄用のコークスや石炭ガス(都市ガスの一種)などを製造する際の原料として用いられています。
一般炭:主に発電・ボイラー用の燃料として用いられています。
石油・天然ガス
太古の生物(プランクトンや藻など)の死骸などが地下に堆積し、地下の高い温度や微生物の分解作用などにより、数百万年から数千万年をかけてできると言われれています。状態により、液体のものが「石油」、気体のものが「天然ガス」となります。天然ガスを-162℃まで冷却して液化したものが「液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)」と呼ばれます。
シェールガス:天然ガスの多くは、砂が固まってできた砂岩の層や石灰岩その他の層の岩石粒子のすきまに溜まっているのに対し、シェールガスは薄くはがれやすい性質をもつ頁岩(けつがん)の層に溜まっています。
シェールガスが眠っている頁岩は、岩石粒子のすきまがほとんどない層であり、在来型のように垂直にまっすぐ井戸を掘るだけでは生産できるガスの量が少なく井戸を掘るために必要なお金に見合うガスの生産量が得られないことから積極的に採掘されていませんでした。しかし、技術の発達によって、井戸を長く水平方向に掘ったり、水の圧力(水圧)を用いて岩に割れ目を作る技術が進歩したことから以前に比べてたくさんの量のガスを安価に生産できるようになり、これまで難しかった頁岩からのガスの採取ができるようになりました。
石油と天然ガスはでき方が同じですので、石油と天然ガスが両方取れる場合も珍しくありません。石油が取れる場所を油田、天然ガスが取れる場所をガス田、両方が取れる場所を油ガス田と呼びます。ただし、これらに明確な差はありません。
油田、ガス田、油ガス田は、地下に存在する炭化水素の状態で便宜上分けているもので、明確な定義があるわけではありません。地下で油分が多い場合は油田と呼び、地下でガス分が多い場合はガス田と呼び、油ガス両方の場合は油ガス田としています。しかし、地下からの採収物が地上に出てきたときには、油田であっても地下で共存していたガスは分離されて出てきますし、ガス田であってもメタン以外の軽量炭化水素分はコンデンセートとして液体として分離されます。(水溶性天然ガスのガス田の場合は、メタンの割合が非常に高く、コンデンセートが含まれません。)