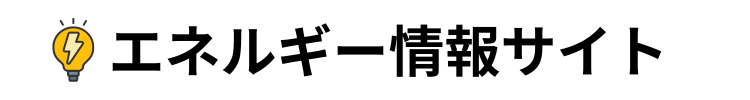原子力発電の問題点・懸念点の一つは原発事故です。仮に事故が発生すれば、周辺住民は避難しなくてはいけません。時によっては多くの方が命を失うかもしれません。そのため、原発の立地には最新の注意が必要です。
浮体式原子力発電は、周辺に人が住まない「洋上」に原発を建てるというコンセプトです。周辺にそもそも住民がいなければ、事故発生時において周辺住民への影響を気にする必要がありません。
日本においても浮体式原子力発電に関する議論が開始されています。
産業競争力懇談会(COCN)は3年にわたって浮体式原子力発電に関する研究会・プロジェクトを開催してきていました。
COCNの報告によれば、浮体式原子力には以下の長所があるとしています。
(1) 津波、地震の原子力発電所に対する影響を大幅に小さくできる
(2) 原子炉からの崩壊熱除去のために、周辺にある大量の海水を動力なしに利用できる
(3) 陸地から離れた沖合に位置することで事故時の住民避難が不要になる
(4) 集中した製造拠点で製造し係留場所に展開することで品質向上やコストダウンが図れる
また、浮体式原子力発電を実現するために、以下の項目について検討しています。
スケジュール・建造費
・建造期間は14.4年程度とし、建造費は陸上の原子力発電と同等と評価
安全設備
- 設計基準事故時に期待する動的機器を4区分として、オンラインメンテナンスが可能なシステムを提案
- 過酷事故時に期待する静的システムを設置し、2区分として多重性と多様性を持たせる
- 海水を活用した半永久的に稼働する静的な崩壊熱除去システムを設置
洋上保守方法
- 浮体式原子力発電設備(原子力発電設備と浮体構造物等)の保守作業のほとんどは、洋上で実施が可能
- 船体の再塗装や大型補修等のために国内にドックの確保が必要
- 揺動場における燃料交換作業等の可否については、今後検討が必要
福島第一事故の教訓からの安全性向上策
- 東京電力福島第一原子力発電所事故において困難を極めた事故時の原子炉減圧操作と原子炉水位計測の多様化について検討
- 減圧操作として、SRV の電源・窒素源の強化および耐環境性に優れたシール材の導入、爆破弁、ラプチャーディスク、電動弁、遠隔手動操作弁、非常用復水器、タービン駆動ポンプによる高圧注水などを提案
- 水位計測として、既存差圧式水位計の改良(凝縮槽の蒸発対策)、超音波による水位計測(原子炉外壁面設置式、計測管式、ガイドプローブ式)、差動型熱電対式水位計、放射線式水位計などを提案
国際連携・国際的な規制
- 放射性廃棄物の海洋投棄について規制するロンドン条約・議定書への対応について陸上と同様の運用が可能であり、特に課題はないことを確認
周辺に住民がいなければ、事故時の避難計画が必要なくなりますので、立地の障壁が下がります。原子力発電は今後も重要な電源であり続けることから、浮体式原子力発電も引き続き検討が進めていって欲しいものです。
【参考】
浮体式原子力発電研究会(産業競争力懇談会 2020年度 研究会 最終報告)
浮体式原子力発電(産業競争力懇談会 2021年度 プロジェクト 最終報告)
浮体式原子力発電(産業競争力懇談会 2022年度 プロジェクト 最終報告)