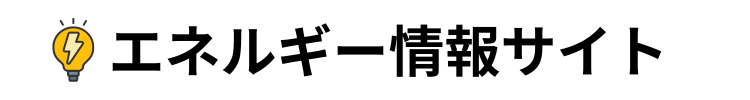最近注目を始めている「ブルーカーボン」についてまとめてみました。
海の植物は、海水に溶けている二酸化炭素を光合成で吸収します。このような海の植物は枯死後、海底へ堆積していきます。このようにして二酸化炭素を海底で貯留する手法をブルーカーボンと呼びます。また、このような植物を「ブルーカーボン生態系」と呼びます。
日本では、①海草藻場(アマモなど)、②海藻藻場(ワカメ・昆布など)、③湿地・干潟、④マングローブ林などのブルーカーボン生態系があり、それぞれ炭素貯留のメカニズムが異なります。
ブルーカーボンでどのくらい二酸化炭素が吸収できるのでしょうか。
環境省によれば、日本の二酸化炭素排出量は2022年度時点で約10億8500万t-CO2と評価されています。また、林野庁によれば、2022年度の森林による二酸化炭素吸収量は5020万t-CO2と評価されています。
桑江らの論文によれば、日本の沿岸域におけるブルーカーボンによる二酸化炭素吸収量は2019年時点で130~400万t-CO2と推計されています。
では、ブルーカーボンを人工的に促進することはできるのでしょうか?
以下に令和4年度(2022年度)にJブルークレジット申請されたプロジェクトトップ5を示します。
Jブルークレジットとは以下の通りです。
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] が、独立した第三者委員会による審査・意見を経て、認証・発行・管理する独自のクレジットであり、一般的な国際標準とされる100年間以上の長期にわたって沿岸域・海洋に貯留され、大気中から除去されるべきCO2の数量を客観的方法論に基づき科学的合理的に評価・算定し、これを認証・発行しております。
令和4年度(2022年度)Jブルークレジット®申請・発行情報一覧(2022年12月26日現在)(t-CO2)
1位:岩手県洋野町(ひろのちょう)における増殖溝ぞうしょくこうを活用した藻場の創出・保全活動(3106.5)
2位:尾道(おのみち)の海のゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり(130.7)
3位:関西国際空港 豊かな藻場環境の創造(103.2)
4位:岩国市神東(しんとう)地先におけるリサイクル資材を活用した藻場・生態系の創出プロジェクト(79.6)
5位:北海道増毛町(ましけちょう)地先における鉄鋼スラグ施肥材による海藻藻場造成(49.5)
岩手県洋野町が圧倒的の3000t-CO2ですが、それ以外は100t-CO2からそれ以下という状況です。
洋野町では約50年前から、岩盤に溝(増殖溝)を掘り、ウニやアワビ漁に利用してきました。この増殖溝178本の総距離は17.5km、幅は約4m、深さは約1mにわたるというかなり大がかりなプロジェクトです。洋野町はあくまでウニやアワビ漁に利用してき溝が二酸化炭素吸収にも役に立っているということであり、このようなプロジェクトを二酸化炭素を吸収させるためだけに実施するのは、コスト的に採算が合わないでしょう。
人工的にブルーカーボンを促進するためには、もう少し工夫が必要かもしれません。
【参考】
2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について(環境省 2024年4月12日)
2022年度森林吸収量の算定結果(林野庁)
我が国におけるブルーカーボン取組事例集(環境省 2023年12月)
浅海生態系における年間二酸化炭素吸収量の全国推計(土木学会論文集B2 2019年)