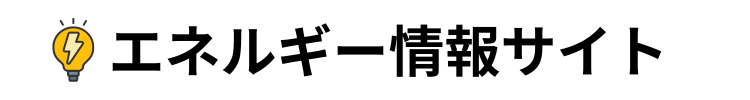エネルギー基本計画とは国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す計画です。2002年に成立したエネルギー政策基本法に基づき、おおむね3年ごとに見直されています。経済産業省が有識者を集めた総合資源エネルギー調査会の中で議論され策定されます。
第5次エネルギー基本計画
2030年の長期エネルギー需給見通し(2015年7月経済産業省決定)の実現を目指しており、その内容は以下の通りです。
・再エネ:22~24%
・原子力:20~22%
・LNG:27%
・石炭:26%
・石油:3%
再エネの配分は以下の通りです。
・地熱:1.0~1.1%
・バイオマス:3.7~4.6%
・風力:1.7%
・太陽光:7.0%
・水力:8.8~9.2%
第6次エネルギー基本計画
第6次エネルギー基本計画では、2030年度の電源構成を以下のように設定しています。
2030年度におけるエネルギー需給の見通し(資源エネルギー庁 2021年10月)
・再エネ:36~38%
・原子力:20~22%
・LNG:20%
・石炭:19%
・石油:2%
再エネが36%とかなり伸びているのがわかります。2023年時点で太陽光は約10%に到達していますが、その伸びは鈍化しており、風力も期待が持てないことから達成は難しい状況かもしれません。
日本国内における太陽光発電の導入状況(エネルギー情報サイト 2024年12月31日)
第7次エネルギー基本計画
第7次エネルギー基本計画策定時点で2024年ですから、2030年度の目標設定は避けたようです。この計画では、2040年度の電源構成を以下のように設定しています。
2040年度におけるエネルギー需給の見通し(資源エネルギー庁 2024年12月)
・再エネ:40~50%
・原子力:20%
・火力:30~40%
再エネの配分は以下の通りです。
・地熱:1~2%
・バイオマス:5~6%
・風力:4~8%
・太陽光:23~29%
・水力:8~10%
本目標を達成するためには、太陽光の伸びが重要となりますが、先に述べたように現在の太陽光発電は伸びが鈍化していますから、その達成は微妙です。
風力発電も2022年時点で1%程度であり、後15年で7~8倍まで増やすことができるのか、はなはだ疑問ではあります。
目標を高く持つことは重要ですが、現実味に欠けるという印象は否めません。